『悲愁物語(1977年)』~「三協映画」魔のトライアングルより生まれし鈴木清順の色彩遷移アクション~
1.『三協映画』~ 魔のトライアングル
三協映画とは何か。それは三つの異なる世界が交差する魔のトライアングルです。
まず一つ目は梶原一騎に代表される漫画・劇画の世界です。
『巨人の星』や『あしたのジョー』に代表されるスポ根漫画の原作者として知られる梶原は映画『愛と誠』の成功によって自身の興行的あるいは文芸的欲望を満たすものとして映画製作会社を設立します。
次に二つ目は藤岡豊に代表されるテレビアニメの世界です。
『未来少年コナン』のダイス船長のモデルとも言われる藤岡さんですが、その黎明期より東京ムービーを立ち上げ、梶原原作漫画の『巨人の星』や『あしたのジョー』といったアニメを手がけることになります。
最後に三つ目は川野泰彦に代表される実写映画の世界です。
日活から石原プロモーションの映画の製作者となり、『愛と誠』のTV版プロデューサーであった彼は格闘技映画と文芸映画といった梶原の極端に異なる嗜好を実写映画として実現する立場を担うことになります。
この異なる三つの世界の製作者が「三人で協力する」ものして命名されたのが「三協映画」です。まぁ、今でいうところのメディアミックス戦略みたいなものでしょうか。漫画→アニメ→実写映画というのは当時飛ぶ鳥落とす勢いの梶原一騎にとっては自然な商流といえるものだったのでしょう。
三者三様の思惑はともかく、その魔のトライアングルから生み出されしモノは一体何か?それは日本映画史上最凶といってもいい『悲愁物語』という映画です。
ここで梶原のwikiより三協映画に関する記述を引用してみましょう。
三協映画では、文芸路線、格闘技路線、梶原原作漫画のアニメ化の三つの路線があったが、経営的には格闘技もので上げた収益を文芸もので使い果たすことの繰り返しであった。なお、1977年に自身の原案をもとに、鈴木清順監督に10年ぶりの作品『悲愁物語』を撮らせている。
どうも梶原一騎が格闘技もので上げた収益をつぎ込んだ道楽のおかげで鈴木清順が10年ぶりに映画を撮らせてもらったみたいな物言いに聞こえなくもない記述ですが、実際そうなのかもしれないのが困ったところです。
『殺しの烙印(1967年)』で日活をクビになり、いわゆる「鈴木清順問題共闘会議」で裁判を起こした清順さんはその後10年も映画が撮れない時期が続きました。
この頃のことは「日活と係争中の監督をほかの会社で使う訳がないよね。でも、それを覚悟でこっちは裁判をやった訳ですから」と清順さんは語っています*1。
たった3本のTVドラマといくつかのCMの演出で糊口をしのいだこの10年間の苦汁の空白の時期に終止符を打つことができたのは、メジャー五社とはしがらみのない独立系ワンマンの製作会社と、メジャーからはお呼びのかからない(女性映画にも実績のある)ワケありの映画監督との利害関係が幸運にも一致した一期一会の結果とも考えられます(この二年後『石川啄木の秘密』というオカルト映画(ん?)が同様のスタッフで企画されたようですが残念ながら実現には至りませんでした)。
『悲愁物語』が文芸ものであるかどうかはともかく、この映画の前半は原案である梶原一騎が得意とする一種のスポ根物として開始されます。
そしてその主人公は「白木葉子」という言わずもがな『あしたのジョー』のヒロインである白木財閥のお嬢様の名を芸名とする素人の新人女優が務めています。
白木葉子演じるプロゴルファーが、特訓に特訓を重ねた上、勝利を勝ち取って芸能界でも活躍するというシンデレラストーリーとその転落、というメロドラマともサスペンスとも取れる物語がこの映画の最初の原案です。おそらくこれは女優を売り出すというある種の道楽的な動機から企画された映画である事は想像に難くありません。
と、まぁ企画意図通告りに両者の利害が一致しているのはせいぜい映画の前半30分くらいではと思います。なんせ清順さんの映画ですからね。一筋縄には行きません。
原案から具体的な商業映画を作るためには監督や脚本家の肉付けが必要ですので色々と策を練ったのでしょう。案の定この映画は暴走を始め、後半から別の映画のようにガラッと変わって清順さんの(負の)サービス精神というか十年分のルサンチマンがこれでもかと炸裂する狂暴なサイコスリラー/アクション映画に変貌します。
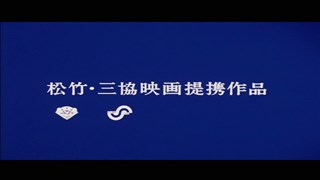


(ちなみにこの映画のタイトルバックはゴルフボールとゴルフクラブが即物的に次々と現れます、なんかゴルフ会社のコマーシャルみたいですね)
2.『魔女狩り』~魔のトライアングルを結びつける一人の男
さてこの三協映画魔のトライアングルの異なる三つの点と点をつなげるためには重要なピースが一つ欠けています。
三つの異なる点それぞれと深い関係のある悪魔に委ねられた*2キーマンが存在するのです。
それは一体誰なのか?
そう、答えは簡単、大和屋竺さんです。日活映画の助監督から脚本家となり、実写とアニメの垣根を軽々と超え、場合によっては殺し屋からミイラ男まで俳優として演じ、その忘れらない憂いた歌声を『殺しの烙印』の冒頭で披露した大和屋さんです(本作ではワンカットだけ豆腐屋でカメオ出演しています)。
大和屋さんは清順さん門下といえる具流八郎のメンバーでありますが、一方で学生の頃は稲門シナリオ研究会で山崎忠昭さんの後輩でもあります。
『野獣の青春』の脚本家で日活映画とも関係の深い*3山崎さんは一方でまたテレビアニメの黎明期に多数の脚本を手掛けていたことで知られています。
その山崎さんが第一話を担当する『ルパン三世 (TV第1シリーズ)1971年』での第二話(傑作「魔術師と呼ばれた男」)を皮切りに、大和屋さんも『ガンバの冒険』、『元祖天才バカボン』、『あしたのジョー2』といった藤岡豊さんが社長を務める東京ムービー(新社)制作のテレビアニメの脚本を次々と手掛けることになります。
本作の後に清順さんが『ルパン三世 (TV第2シリーズ) 1977年~1980年』に途中から監修で参加するのもこの人脈からは至極自然な流れといっていいでしょう。
さて、話を『悲愁物語』に戻しますと、この映画は元々「魔女狩り」の題のシノプシスがあってそれを元に大和屋さんの脚本が作られています。
「魔女狩り」というには魔女と魔女を狩る者が必要になりますが、この映画では魔女を狩る者が魔女のような狂った女で、スターである普通の女が魔女狩りにより侵食されてしまうという設定になっています。
その設定を清順さんはどのように演出したのでしょうか?以下にその描写を具体的に検証してみましょう。
(注:以下ネタバレ解説します。)
3.緑色の魔女 ~ 色彩遷移のアクション映画
みなさんは魔女というとどのような姿を想像しますでしょうか?三角帽子で箒に乗ったり、真っ赤なリボンをつけて宅急便稼業に精を出したり、とまぁ色々あるかと思いますが、この映画では江波杏子扮する普通の主婦(といっても狂っているので全然普通じゃないのですが)が魔女の役割を演じます。
彼女が魔女のような狂った女であることは「緑」色で示されます。
つまりこの映画には登場人物それぞれに色の設定があるのです。
具体的に色の意味は以下になります*4
- 緑ー狂、不安の色
- 白ー少年
- 黄ー生
- 黒ー死
- 赤ーいんらん
- ピンクー好きな色(だから『悲愁物語』の台本の表紙はこの色だ)
登場人物に置き換えると緑は狂った主婦の江波杏子、

白と黄色(の部屋)は弟役の少年、


赤は主人公の恋人でゴルフ雑誌の編集長である原田芳雄です。

赤と緑は敵対関係にあるので赤vs緑が対決するアクションシーンがあったりします。


一方主人公で魔女狩りの被害者である白木葉子には色がありません。彼女は色がない女なので接触してくる他者の色に侵食されてしまいます。
(以下は最初の登場シーンであるモノクロの広告素材。だんだん色がついて「初夏の風、バーディチャンス!」の広告になります)



白木葉子に関してはマニキュアの色でどの色に侵食されるかが視覚的に描写されます。
- 赤(原田芳雄)と接触→赤いマニキュア



- 緑(江波杏子)と接触→緑(または黒)のマニキュア



- 白(少年)と接触→黄色のマニキュア


- ピンク(桜の花びらの血痕)を経て最後は黒(死)→黒のマニキュア



どうでしょうか。とても単純で分かりやすい演出ですね!
ハリウッドの色彩設計とは一線を画す大胆かつ過剰なまでにサービス精神旺盛な演出といえます(まぁ、普通の人はこんな変なことはしないのでしょうけど...)。
とはいえこの映画の分かりやすいところ(?)はこの色彩遷移ぐらいです。
「訳の分からない映画を撮る奴はいらない」と日活の社長からクビになった元凶でもある『殺しの烙印』も相当凶暴な映画でしたが、こちらの方がカラー映画でやりたい放題やっている分、さらに凶暴で清順度が増していると私は思います。
さすが清順/大和屋の最凶コンビです。
「No.1は誰だ?」そうです彼らこそ“日本映画史上最凶No.1”です。
何が最凶かということに関しては特にここでは触れませんのでご自身の目で確認なさってください。魔のトライアングルに吸い込まれて遭難して戻ってこれなくなる危険性がありますが、それもまた映画を見る楽しみに他なりません。